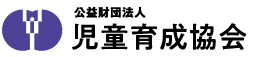令和6(2024)年の国内出生数の速報値は過去最少の72万988人でした。さらに、今後発表される確定値は69万人前後になると予測されています。この数値は国立社会保障・人口問題研究所が、昨年公表した将来推計より15年早いペースで進んでいます。
ふり返れば、わが国は昭和50(1975)年から現在まで少子化現象の一途を辿っています。特に平成元(1989)年の「1.57ショック」以降、政府は少子化対策に取り掛かってきましたが、50年間出生数の減少に歯止めがかからず、近年では少子化はむしろ加速化しています。
この推移を見ると、人口減少の要因分析や対策に学際的な叡智を集めた調査研究が不十分だったのではないかと思ってしまいます。また、少子化について国民に十分な情報共有を図ると共に、今を生きる「現世代」には、この国の文化を「将来世代」に継承していく大切な責任があることを、正面から問いかけてこなかったのではないかとも思われます。
これらのことを考えますと、社会・国家を維持するのに必要な人口を定常状態に保つために、今、私たちが出来ることをするしかありません。それは、子どもたちが「この世は生きるに値する⋯⋯」と、生まれたことの喜びを心の底から感じられる環境を、お為ごかしでなく、こどもをまんなかに据えて科学的にいちから見直すことだと考えます。
さて、近年の「子育ての経済学」の知見を参考にしますと、子どもが育つ環境は大切で、子どもには優しさと敬意をもって接するようにして、しつけなども厳しすぎないようにして、優しく育てても、子どもはしっかり成長するということが示されています。
そして、このことについては目新しいことではなくて、江戸時代中期、鍋島藩の山本常朝が武士としての心得を口述した『葉隠』でも、子育ては、脅したり騙したり、自然への恐怖をうえつけたり、強く叱ったりしないようにと戒めており、のびのびと育てれば臆病にならず内気になることもないと記しています。
どうでしょうか。子どもたちは、セルフエスティーム(自尊感情、自己肯定感、自己効力感、自己有用感)が高まり、自分を信頼して育つことができれば、困難に出会っても、何かにつまずいてもそれを経験として活かして生きて行けるようになるでしょう。このセルフエスティームを高めることには、幼少期から、親や地域の大人たちや友人・仲間から認められる経験が大変重要になります。そこで、保育所や児童館・放課後児童クラブ・青少年交流センターの果たす役割がとても大切になります。
当協会はその一助となればとの思いで、すべての子どもが健全に成長・発達できる社会の実現に寄与することを目的として以下の事業を推進しております。
企業主導型保育事業では、子ども・子育て拠出金を負担している企業等が従業員のために保育施設を設置・運営している場合、運営費を助成しております。令和6年度は約4,400施設に助成実施しました。また、保育施設職員の質の向上のための研修会を実施すると共に、施設と協会の「絆」を深めることに注力しております。さらに、助成金申請に際して作年度からは新方式の「公金管理システム(PMMS:ピムス)」を本格的に導入して、施設職員の方々の申請業務の効率化を図ってきました。
健全育成事業では、児童館・放課後児童クラブ、青少年交流センター等8施設6事業を地方自治体から託されて運営しております。
児童給食事業では、低カロリーでビタミン・カルシウム等幼児の成長にとって栄養価が高いスキムミルクを、全国を対象にして要望をいただいている保育所、児童福祉施設等に安価で配分しています。
児童養護施設等サポート事業は、児童養護施設を退所後大学等に進学するなど、働きながら自立援助ホームなどで自立生活を始める児童と青少年に対する支援を行っています。
その他、児童福祉関係の研修・研究等への協力事業、出版・監修事業等々の公益事業を時宜に応じて行っております。
さて、文末になりましたが、わが国は大変地震の起こりやすい地理的環境に位置しております。また、近年では感染症対策が大きな課題となりました。子どもの生命の保全と健康維持のために、防災や感染症に対する緊張感も持続させながら、日夜すべての子どもの幸せのために邁進されている方々をしっかりと支援できるように、私ども協会も一層研鑽を積んで参ります。
鈴木一光